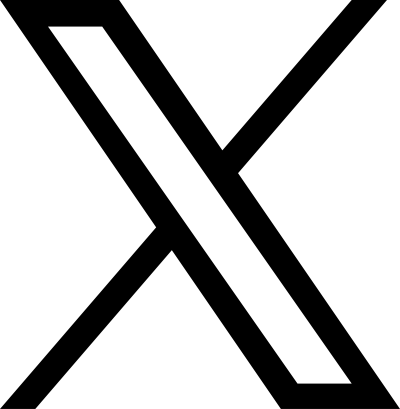なぜ、今、アジア?
アジアの中の国立がん研究センター中央病院とは?
国立がん研究センター中央病院はこれまで、欧米や韓国、台湾、香港、シンガポール等と臨床研究の分野で緊密なパートナーシップを築いてきました。ATLASプロジェクトでは、こうした国に加えて、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア等のアジア各国へも連携先を拡大して、がんの治療開発に取り組んでいきます。
なぜ今アジアなのか?
アジアは世界の人口の6割を占めています。今後、アジア諸国では経済発展が進むと同時に、日本のような高齢化が急速に進んでいきます。こうした背景から、今後がん患者が特にアジア地域で急速に増えることが予想されます。一方、日本に目を向けてみると、2020年に日本で新しくがんと診断された患者さんは米国の45%、ヨーロッパの23%にとどまっています。また、2050年には日本の人口は1億人を下回ると言われており、日本だけでは大規模な研究を行うことが困難となります。しかし、アジア各国が協力することで大規模な研究を迅速に実施することができるようになります。実際、ATLASで連携するアジア諸国で、新しくがんと診断された患者さんの数を足し合わせると年間200万人を超え、米国とほぼ同数となります。
さらに、アジアでは胃がんや頭頸部がん、胆道がん、子宮頸がんなどに罹患される方は、米国やヨーロッパよりもはるかに多いことが知られています。しかし、これまでがんの治療開発は欧米主導で進んでいたため、アジア特有のがんに対して必ずしもより良い治療が多く生み出されてきたとは言えません。これらアジア特有のがんについては、アジアが主導的に治療開発を行う必要があります。
こうした背景から、日本だけでなく、アジア全体でがんの治療開発が進むようなネットワークが必要です。アジア全体で臨床研究を行うことで、アジア特有のがんに対して、より迅速に多くのより良い治療が生み出されることが期待できます。これこそがアジアでATLASプロジェクトを行う意味となります。
アジアの人々とどのように協働するのか?
では、がん患者さんが多いというメリットがあっても、各国が足並みをそろえてがんの治療開発、特に治験を行うことはできるのでしょうか?
私たちは出来ると信じています。ATLASに参加する医療機関は、それぞれの国で最も多く治験を実施している機関から選定されています。さらに治験を高い品質で実施できるようにATLASプロジェクトを通じて、人材や機器など治験実施基盤の強化が行われています。また、教育面での交流も進んでおり、オンラインでの教育セミナーやシンポジウムが活発に開催されています。実際に日本が企画して、アジア諸国が参加するような国際共同研究が複数並行して開始されており、こうした実際の研究を通じて、ATLASネットワークがより強固なものになると期待しています。