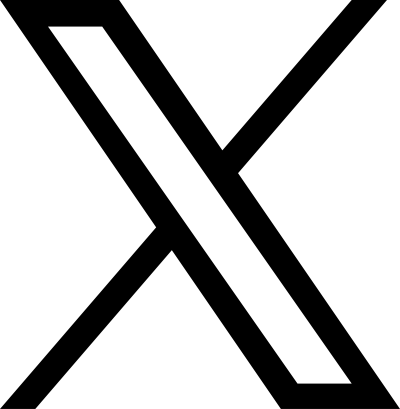医師主導治験って何?
はじめに
皆さんや皆さんのご家族が病気になった時、病院や薬局でもらった薬で、その病気が治ったり、症状が楽になったりした経験があると思います。それらの薬が患者さんの手元に届くまで、どのような旅をしてくるかご存じでしょうか?
このページでは治験・臨床試験についてご説明します。
治験・臨床試験とは?
病院や薬局でもらう薬は、概ね医療用医薬品と言われます。これら医薬品が使用できるまでには数々の医学研究、特に「治験」というステップを通っています。 化学合成や、植物、土壌中の菌、海洋生物などから発見された物質の中から、試験管の中での実験や動物実験を経て、病気に効果があり人に使用しても安全と予測されるものが「くすりの候補」として選ばれます。このくすりの候補は開発の最終段階において、健康な人や患者さんの協力を得た臨床試験を通し、人で有効性と安全性を調べることが必要です。こうして得られた成績を国が審査して、病気の治療に必要かつ安全に使用できると承認されたものが「くすり」となります。
(厚生労働省HPより抜粋)これら医学研究のイメージはこの(以下)通りです。
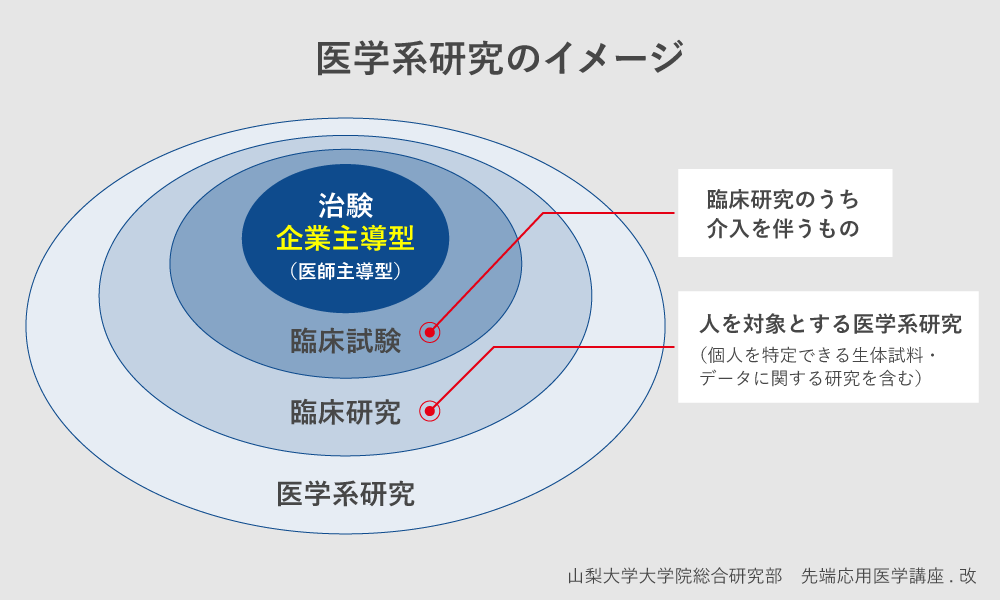
医学系研究のうち、人を対象とした臨床研究(個人を特定できるデータや生体試料を用いる研究を含む)の中で、さらに研究的に薬物を投薬するなど介入を伴うものとして臨床試験があります。臨床試験のうち、「くすりの候補」を用いて国からの承認を得るためのデータを集める臨床試験は、特に「治験」と呼ばれています。
なぜ、治験が必要なのか?
患者さんのお手元に、重大な副作用の危険性がある薬や、有効性が乏しい薬を届けるわけにはいきません。医薬品の有効性と安全性を科学的に証明するためのステップとして治験が必要です。
例えば、日本では治験は以下のようなステップで進みます。
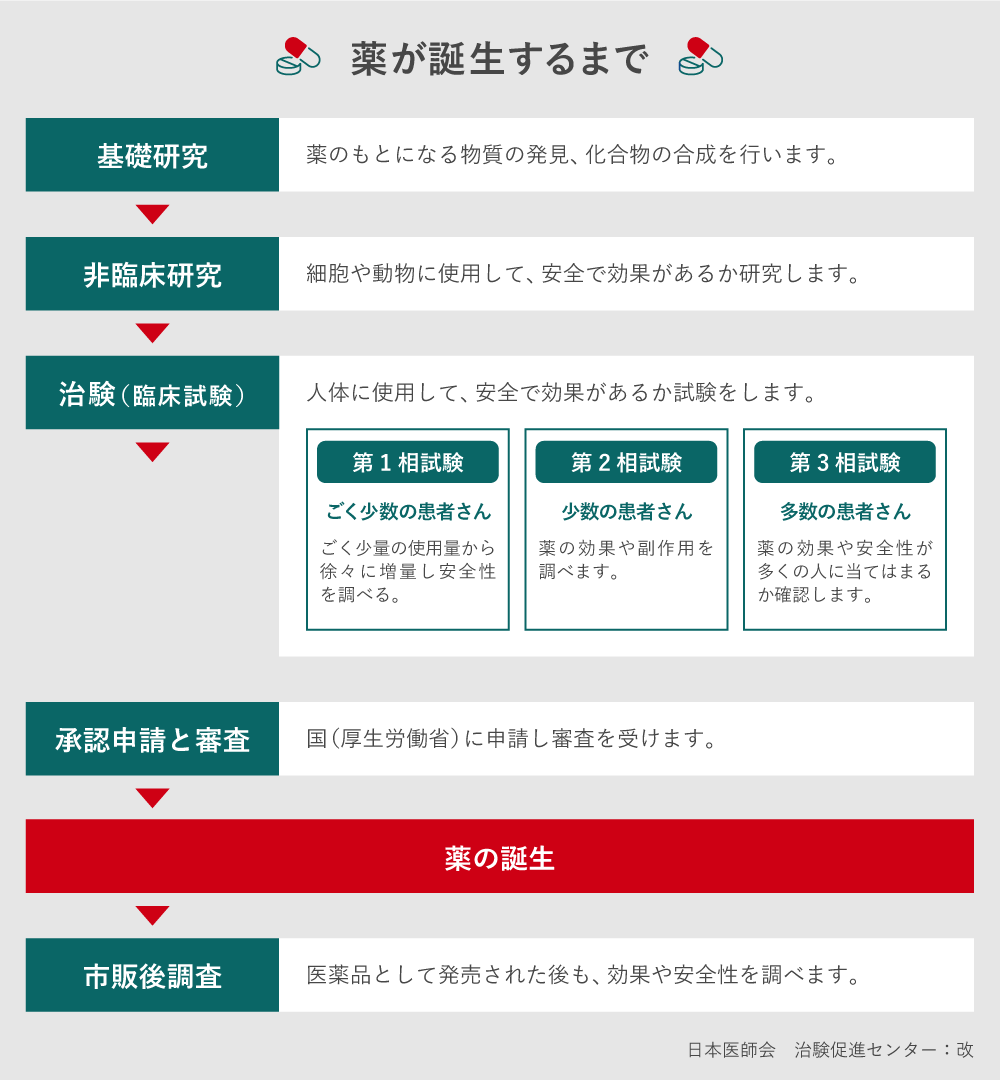
このように、新しい治療法が開発され、現在や未来の患者さんの福音となるために、治験は非常に大切です。病気で困っている患者さんに新しい薬が届くまでには、たくさんの方々の協力が必要となるのです。未来の(自分や自分のご家族も含めた)病気で困っている患者さんのために、治験に参加頂くことは大変有意義なことです。そのため、治験は、未来への贈り物と言われています。
医師主導治験はどんな課題を解決しているか?
治験には主に製薬企業が手がける「企業治験」と、研究者自らが行う「医師主導治験」があります。
従来、治験と言えば主に企業治験を指しました。しかし、昨今は医師主導治験も徐々に活発になってきています。これらの治験は、それぞれの守備範囲が異なります。例えば膨大なコストがかかる大規模な治験は、医薬品の製造販売によって原資を確保できる可能性の高い企業が行います。しかしながら、企業の体力(資金)、努力(マンパワー)にも限界があり、例えば希少疾患と呼ばれる患者数が少ない疾患では、開発になかなか着手できない場合もあります。そうした場合に、研究者が自ら治験を行い、医薬品を開発していくことがあります。これを「医師主導治験」と呼びます。
いずれの治験の目的も、未だ世の中に存在しないより良い医療(Unmet Medical Needs)を創りだしていくことになります。